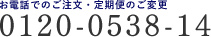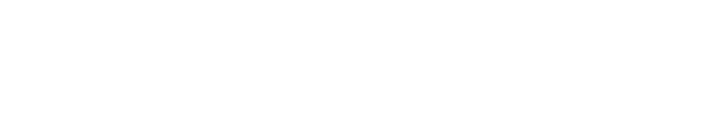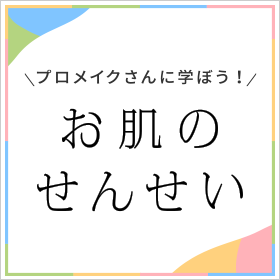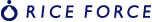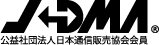いまだ猛暑が続く中、食欲が落ちたり、身体が重だるくなったりしていませんか?“医食同源”という言葉のとおり、健康を保つためには普段からバランスのよい食事を心がけることがとても大切です。手軽においしく栄養補給できる「豆」を味方につけて、夏の不調を乗り越えましょう。今回は料理家で薬膳調理師でもある橋本 加名子さんに、中医学的な観点から豆の持つパワーや薬膳的な働き、毎日の食事に取り入れるコツなどをうかがいました!

- Profile
- 橋本 加名子さん
- > おいしいスプーン
料理研究家、栄養士、薬膳調理師、防災士。発酵とハーブ・スパイスのタイ・アジア料理、ヴィーガン・ベジタイ料理、薬膳、養生、和食の教室「おいしいスプーン」主宰。教室運営のほか食品のプロデュースやコンサルティング、雑誌やウェブなどメディアでもジャンルにとらわれない家庭料理を提案。近著に『毎日の腸活に役立つ 麹豆乳クリームレシピ』(ブティック社)
いま豆を摂るべき理由
中医学では、体内に余分な水分を溜め込んだ状態を「水滞」といい、全身の水の巡りが悪くなって、だるさや食欲不振、むくみなどを引き起こします。高温多湿な日本の夏は「水滞」による不調=夏バテを起こしやすい環境。「豆」の力が、湿度に負けない身体づくりを助けてくれます。

夏バテ解消
薬膳に欠かせない「豆」は、過酷な日本の夏を乗り切るために効果的な食材。暑さで疲れやすい身体のエネルギーを養う「補気」、胃と消化器系の働きを高める「健脾」作用により、だるさや食欲不振、胃腸の不調といった夏バテ症状の改善が期待できます。
水の巡りを整える
夏バテを防ぐには、むくみや重だるさの原因となる体内の余分な水分を排出することがとても大切。豆の「利水」作用が水分の代謝をうながし、全身の水の巡りを整えてくれます。食材には身体を温めるもの、冷やすものがありますが、豆はそのどちらでもない「平性」(一部を除く)であるため、食生活に取り入れやすい点も魅力です。
夏に不足しがちな栄養素が豊富
のどごしのよい麺類だけで済ませたりと、夏の食事は栄養が偏りがち。豆は“畑の肉”と呼ばれるほど多くのたんぱく質を含み、疲労回復に役立つビタミンB1、赤血球の生産を助ける葉酸、ストレス緩和効果もあるカルシウムなど、エネルギー代謝に重要なビタミンや、汗と共に失われやすいミネラルも豊富です。
腸内環境を整える
豆類は食材の中でも群を抜いて食物繊維が多く、便秘の予防や解消に役立ちます。腸内環境が整うと自律神経のバランスもよくなり、また吸収した栄養分がスムーズに皮膚まで運ばれるようになって、美肌に近づきます。
おすすめの豆4選
夏バテだけでなく、豆は美肌や美髪にも力を発揮するスーパーフード。いま味わいたい旬の豆から、季節を問わず入手しやすいものまで、この時期におすすめの4つの豆をクローズアップしてご紹介します。

枝豆
8月上旬から9月中旬が最盛期の枝豆は、今がまさに旬。たんぱく質を筆頭に、代謝を助けるビタミンB群、メラニン色素の生成を抑えるビタミンC、カリウムやマグネシウムといったミネラルなど、夏の身体とお肌にうれしい栄養素がたっぷり含まれています。枝豆のたんぱく質やビタミンB群は、アルコール分解を助ける働きがあり、ビールのお供にぴったり。薬膳的には血を養う「養血」作用もあるので、貧血気味の方にもおすすめです。
小豆
薬膳における小豆は、体熱を取り除き暑さから身体を守る「清熱」作用、余分な水分や老廃物を体外に排出する「利水」「解毒」作用が高く、夏のむくみ対策には非常に効果的。血の巡りをよくする「活血」作用もあるとされ、重い月経痛や夏場に多い冷えのぼせの改善が期待できます。また小豆には強い抗酸化作用があるポリフェノールが豊富に含まれており、アンチエイジングケアとしても◎。
緑豆(リョクトウ)
ベトナムのチェーなど、東南アジアのデザートによく用いられている緑豆は、薬膳の「夏の豆」を代表する食材。豆類の中では数少ない「寒性」に属し、身体にこもった熱を冷やす効果があるといわれています。細胞の生産・再生を助ける葉酸を豊富に含み、美しい肌や髪のためにも意識的に摂りたい豆のひとつです。緑豆は、皮をむいて2つに割った「ムングダル」がインド食材店などで販売されていますが、手軽に取り入れるなら、緑豆もやしや緑豆春雨を利用するとよいでしょう。
さやいんげん
余分な水分を排出し、胃腸の調子を整えてくれるさやいんげんは、夏の疲れが溜まった身体にぴったりの旬食材。抗酸化作用をもつβ-カロテンやビタミンB群、骨を丈夫にするビタミンKも豊富です。生のさやいんげんには、食中毒の原因となるレクチンが含まれているため、必ず十分に加熱してから食べましょう。
豆の“ちょい足し”
アイデア
豆が身体にいいのはわかっていても、下処理が面倒だったり、暑い中での調理が苦痛だったりで敬遠しがち。でもそれではもったいない!毎日の食事に無理なく豆の栄養を取り入れる「ちょい足し」アイデアをぜひ取り入れてみて。

水煮やレトルトを活用
暑い時期に調理のハードルが上がる乾燥豆は、水煮缶やレトルトを活用しましょう。蒸し小豆や水煮の大豆、ひよこ豆やレンズ豆などさまざまな品種の豆がスーパーで入手でき、下処理いらずで手軽です。
加えるだけ!
ちょい足しでラクに「マメ活」
◎サラダや冷奴に
無糖の蒸し小豆をプラスすると、栄養価がグンとアップ。ポテトサラダには枝豆を。枝豆の風味や食感が、じゃがいもとよく合います。
◎カレーに
ひよこ豆や緑豆(ムングダル)がおすすめ。缶詰のひよこ豆のにおいが気になる場合は、一度熱湯に通してから使うと◎。
緑豆は火が通りやすいので、他の材料と一緒に煮込んでOK。身体を冷やす食材ですが、カレーのスパイスが冷えすぎを防いでくれます。
◎スープに
ミネストローネ×大豆や白いんげん豆など、豆はスープとも相性のよい食材。冷たいものの摂りすぎで冷えた内臓も温めてくれます。
◎ネバネバ食材と
オクラや山芋、モロヘイヤ、ツルムラサキなどのネバネバ食材と豆を一緒に摂ると、たんぱく質の吸収率がアップします。ネバネバ成分には胃腸を守る働きもあり、より高い健康効果が期待できます。ごま油やしょうゆとさっと和えれば完成!
ひと工夫で
もっとおいしく健康に
- ・枝豆は市販の冷凍品を利用する手もありますが、旬の時期はぜひ枝付きの生のものを。さやの片側を切り落とし、塩もみで産毛を取り除いて洗い流したら水を少し入れたフライパンで蒸し焼きにし、にんにく・塩・五香粉と炒めると、ビールによく合う香りのよいおつまみに。
- ・乾燥豆を多めに下ゆでし、小分けにして冷凍しておくと、栄養が偏りやすい単品料理にもさっと加えることができ便利です。
- ・豆をお茶として取り入れるのもおすすめ。体内の余分な水分や老廃物を排出する小豆茶や、同様に利水作用、健脾作用があるとされるハトムギ茶や麦茶に小豆をプラスして飲むのもよいでしょう。
橋本さんからのメッセージ
 夏の疲れをそのままにしておくと、ゆらぎやすい季節の変わり目に体調を崩し、不調を次の季節に持ち越すことにもなりかねません。身体は、食べたものでできています。健康も美容も、しっかり栄養のあるものを食べて、腸内環境を整え、質のよい睡眠をとることがとても大切。そうすると自律神経も整い、安定した気持ちで自分と向き合えるようになります。今ある不調は今のうちに解消して、健やかな毎日を過ごしましょう。
夏の疲れをそのままにしておくと、ゆらぎやすい季節の変わり目に体調を崩し、不調を次の季節に持ち越すことにもなりかねません。身体は、食べたものでできています。健康も美容も、しっかり栄養のあるものを食べて、腸内環境を整え、質のよい睡眠をとることがとても大切。そうすると自律神経も整い、安定した気持ちで自分と向き合えるようになります。今ある不調は今のうちに解消して、健やかな毎日を過ごしましょう。